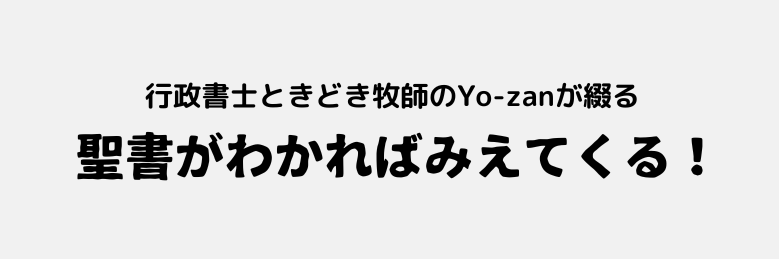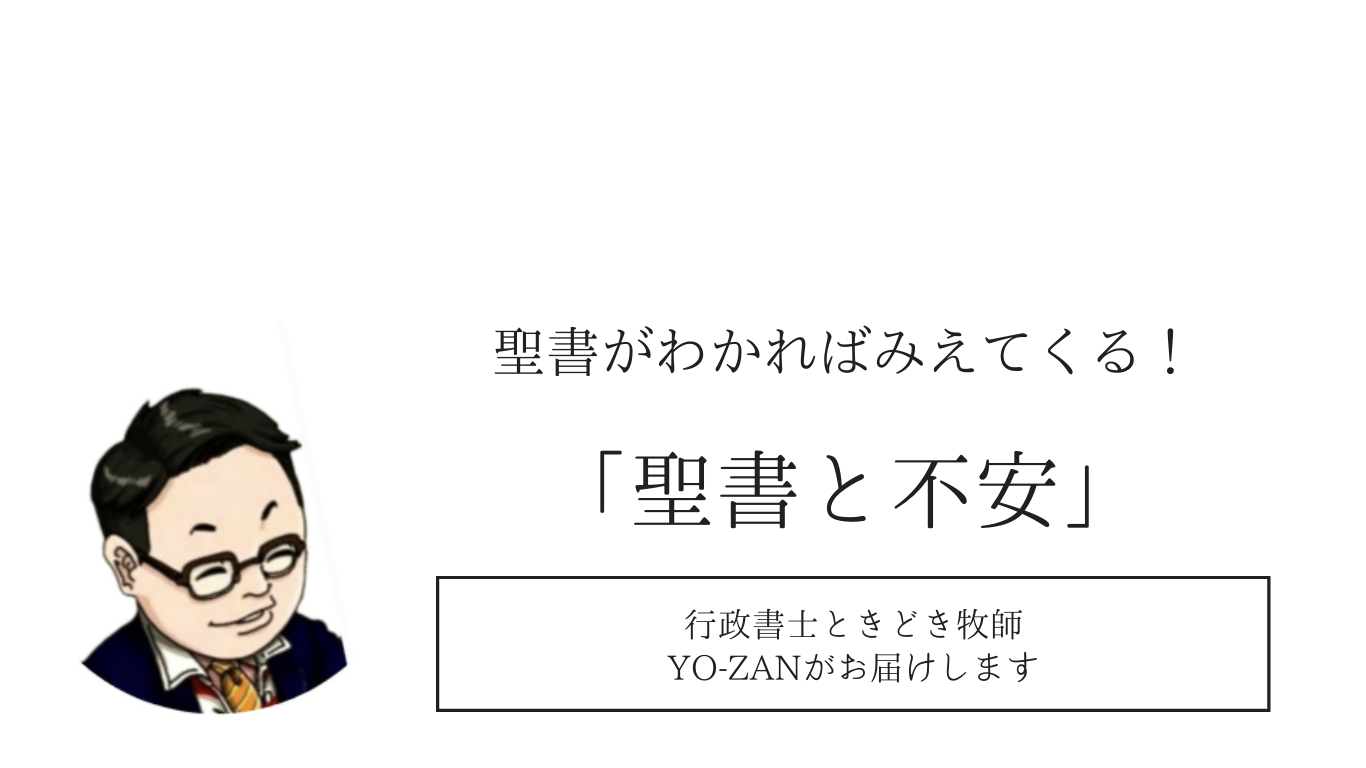不安は良い側面もあるけど不安に振り回されるのはよくない
日本人の不安に関する意識調査によると、75%が「不安を感じている」と回答しています。不安は誰もがもつ感情であり、生物の生存という側面からみても、不安は危険を知らせリスク回避できたり、次にすべきことに備えさせるなど、生きるうえで大切な役割を持つ感情です。なので不安自体は、決してネガティブなことばかりとは言い切れません。
しかし、不安感情が、ありもしないようなことを脳の中に描き、勝手に恐れ、不安が不安をうむような状態になることもあります。このような状態は好ましくはありません。
また、不安が心のキャパシティを超える量となると、自信を失ったり、決断力が低下したり、人間関係に問題が生じたりします。体にも悪影響を及ぼしかねません。小さな不安や悩みでも、いつしか大きくなってメンタル疾患になるケースもあるので、不安は少しずつ解消したほうがいいです。
では、正しく不安に対処するためにどうすればよいのでしょうか?
言語化で不安は軽減される
心理学の研究によると、不安に対処する方法の一つに、「不安の原因を知る」こと、この気づきが大切だとされています。しかし、不安な心と向き合い、その原因を見つけることは簡単なことではありません。不安に向き合うことは、時に自分の恥ずかしい部分、ダメな部分と向き合う行為でもあるため、できるなら避けたい行為です。
また、人間の脳は、不安といったネガティブな感情が、自分の人生を支配してしまうのではないかと必要以上に恐れ、表面化せずに、無理やり抑え込もうとする特性があります。つまり、不安の原因を知る前の段階で、不安の感情を無かったものにしようとしてしまうので、原因の追究ができなくなってしまうのです。その結果、ネガティブな感情で脳のキャパシティが埋め尽くされ、作業領域がそこまで広くない脳がキャパオーバーし、思考力が低下した状態になり、ますます不安や悩みの解決からは遠くなってしまいます。
よって、まず第一にすることは、不安を無かったことのように扱わず、意識下の領域に引き上げ、不安である事実をそのまま可視化し、勇気をもって自分の心と向き合い、不安そのものを「言語化」していく作業が大切になってきます。不安の言語化によって、脳が不安の感情を論理的にとらえ、不安そのものの根本原因を分析し、解決策も具体的に描けるようになってきます。言語化することができ、その不安が客観的、具体的になれば、その不安や悩みの9割は解決できると言われています。
聖書にはその「言語化」ための具体的な知恵が書かれてあります。
不安を言語化する聖書の知恵「話す、書く、祈る」
- 安心できる誰かに自分の不安を話して言語化する
「互いに励まし合い、互いに教え合い、互いに訓戒し合い、キリストの愛をもって互いに仕え合いなさい。」
(ローマ人への手紙 15:14)
「互いに励まし合い、教え合い、訓戒し合う」とは、すべて言葉による媒介を前提とした言葉です。つまり、自分の思いを言語化するためには、対話が有効手段であることを示しています。自分一人ではなかなか言葉にできない思いも、他者に語ろうとする中で少しずつ言語化できるようになります。
誰かからの共感を得ると、人の心は軽くなります。相談は時に恥ずかしいことでもありますが、勇気を出して、自分が安心できる、相談したいと思う人に話してみましょう。今まで不安に思っていたことも悩みの一部ではあったけど、根本は「誰にも相談できない。誰にも共感してもらえない、理解してもらえない。そんな孤独に悩んでいた。それが一番の不安・悩みだった、その事に気が付いた」というケースもあります。
人は誰しも不安を抱えることがあります。そんな時、励まし合い、教え合い、共感を得られる相手に言語化していくことは、不安を乗り越える上でとても大きな力になりますね。
その相手はたくさんの人でなくていいのです。一人でいいのです。
- 自分が安心できる人を想像し、その人に手紙を書いて言語化する
実際に自分の思いをしっかりと敬聴してくれるだけの人がすぐに見つからないということもあるかもしれません。その時は、信頼できる相手に手紙を書くようにして、自分の思いを言語化してみます。相手の年齢、性別、関係性、趣味、職業など、より具体的に想定することで、より言語化しやすくなります。
聖書に出てくる人物たちも、自分の不安を神様に文字に書いて表現する場面が数多く書き残されています。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって守ってくれます。
(ピリピ4:6〜7)
言語化を通して、自分の不安を知ってもらう、ただそれだけでもきっと心が軽くなります。
- 祈りで言語化する
「神よ、私の祈りに耳を傾けてください。私の願いに目を留めてください。私は悩み苦しみ、声を上げて泣き叫びます。私の心は激しく動揺し、死の恐怖が私を襲います。恐怖とおののきと苦しみが私に降りかかります。」
(詩篇55:1-5)
祈りについては、聖書に出てくるさまざまな立場に置かれた人たちの、神様にささげる祈りが記されています。祈りの相手である「神」ご自身についても具体的に書かれています。
先に挙げた聖書の言葉を記したといわれるダビデは、自分の不安を神に語り掛けています。彼は周囲からの暴力や裏切りに直面していながらも、リーダーとして強くあらねばという思いから、誰にもその悩みを打ち明けることができない状況にしました。そんな不安や悩みを抱え続けていたダビデは、聖書に記されている神を頭の中に思い描き、その神に語り掛けるように、自分の気持ちを隠さずに打ち明けています。自分の悩みや不安を言語化しているのです。言語化しきったダビデは、その後、願いという形で、不安の感情を味方につけ、自分に必要なものを具体的な言葉にしていきます。
「神よ、私の願いを聞いてください。私の敵から私を守ってください。あなたは私の避難所です。あなたは私に力と平和を与えてくださいます。」
(詩篇55:16-18)
ダビデは神に祈ることを通して自分の悩みを言語化し、不安を客観視できるようになりました。その結果、危険を回避し、自分自身が成長し続けるために必要なものを求め始めるようになったのです。
私たちもダビデのように、不安に支配されるのではなく、不安を祈りの言葉に変えて、不安を有効利用していきたいですね!
「初めに、ことばがあった」から読み解く「不安の言語化」
「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。」
(ヨハネの福音書1章1節)
「初めに、ことばがあった」とありますが、これは聖書の原語であるギリシャ語の慣用句で、「かたちのないものを言葉にする」という意味があります。かたちのないものというのは、人間の感情も含まれています。
さらに、聖書では、「ことば=神」であるとされています。つまり、かたちのない感情を言葉にすることは「神」を体験するほどにすばらしいことだということを意味しています。
不安という目に見えない感情を言語化し、かたちにすることで、人間の脳は、「不安」という感情を、論理的・客観的に受け止めるように働きます。神と表現されている「ことば」は、聖書の原語では「ロゴス」という単語が用いられています。「ロゴス」という単語は、「論理」とも訳される言葉です。
つまり、感情を「ことば」にするということは、感情を「論理的に考える行為」です。感情を論理的に考える中で、不安が持つ機能を冷静に判断することができるようになります。
感情は右脳の働きですが、感じていることを言語化するプロセスを実践し続けていくと、論理的思考をつかさどる左脳が動き始めることが、脳科学の研究でも立証されています。つまり、感情を言語化するだけで、本来右脳の働きであった「不安」という感情を、左脳の働きによって「論理的・客観的に」考えるようになるのです。
その結果、不安の感情はネガティブな側面ばかりではなく、私たちに危険を知らせたり、自らの成長にとって避けるべきこと、取り組むべきことを見出すために大切な感情であることを、言語化という習慣と体験を通して知ることができるようになっていきます。
その積み重ねの先に、今よりも更に成長した自分との出会いがまっています。不安が自分の心をネガティブな方向に誘おうとするときは、意識的に言語化し、不安を客観視し、深掘りし、意味あるものとして活かし、「この不安は自分の成長の材料になる味方だ!」と捉え、不安に向き合っていきたいですね。
「明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は,その日だけで十分である」
マタイによる福音書 6:34
ケセラセラ