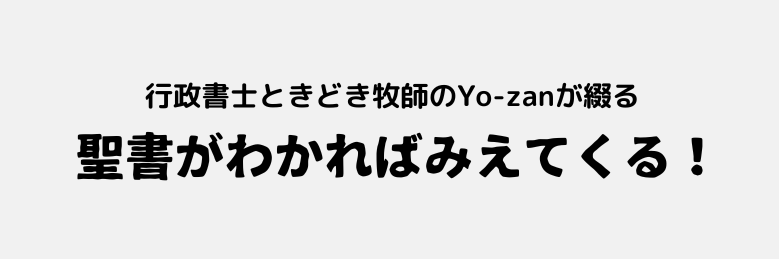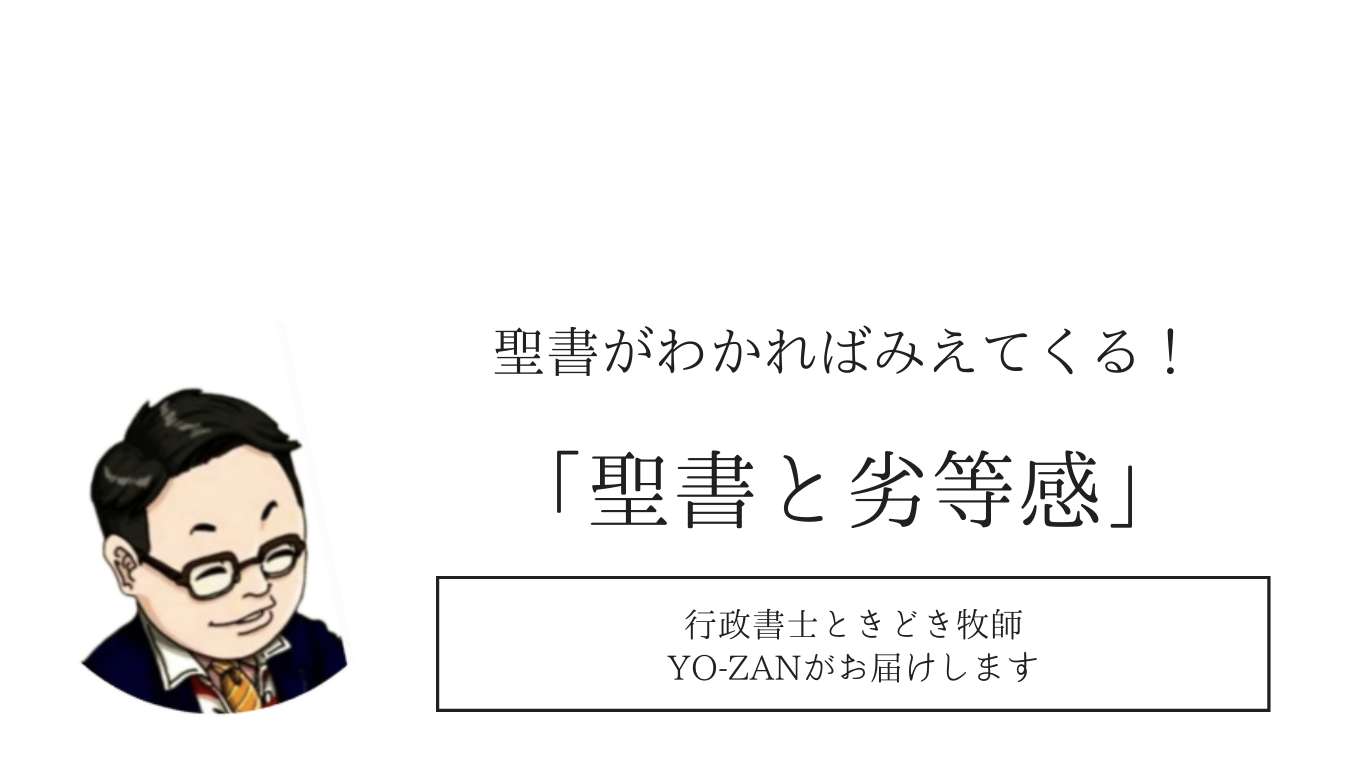劣等感がもたらすもの
劣等感とは、自分が描いている理想と現実の自分を比較したときに感じる感覚を表現した言葉です。20代~50代を中心とした統計データによると、「劣等感を持っていない人は一人もいなかった」という結果がでています。ほとんどの人が何かしらの劣等感を抱いています。
しかし、劣等感を持つこと自体は問題ではありません。劣等感を過度に持ちすぎることに問題があります。劣等感に囚われすぎるあまり、無気力になってしまうケースもあります。さらには、人を避け、孤立し、社会の中で生きることが困難になってしまうことも。そんな中、この劣等感を避けようとする人も多くいます。無理やりなポジティブシンキングで、劣等感がまるで自分の内にないかのようなふりをしてしまうのです。けれど、このやり方は非常に危険です。蓋をしても劣等感はなくならないどころか、その度合いはさらに高くなってしまうのです。劣等感を過度に恐れるようになると、自分の心だけでなく周りにも悪影響を及ぼすこともあります。劣等感が強いあまり、ちょっとしたことに過剰に反応したり、他者を攻撃したり、犯罪に至るという最悪なケースもあります。聖書に出てくる人類最初の殺人も、劣等感から生じた嫉妬による殺人でした。最初の人アダムの二人の息子である、カインがアベルを殺害したのです。劣等感がコントロールを失うと、こういった悲しいケースも生み出してしまいます。
劣等感をコントロールするための聖書からの知恵
劣等感に自分の心がマイナスに左右されないためにはどうすればよいのでしょうか?新約聖書の多くの部分を記した、「パウロ」という人物。彼は聖書だけでなく世界史の教科書にも出てきます。当時、多くの信徒がいた教会のリーダー格であったパウロの言葉から、劣等感をどのように扱っていけばよいのかを読み解いていきます。
1.劣等感があることを認める
「ですから私は、 キリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、 迫害、困難を喜んでいます。」
新約聖書
この「弱さ」という言葉は、新約聖書の原語であるギリシャ語においては、フィジカル的な弱さというよりも他者と比較して自分が劣っていると感じている、そんな精神的な脆さを意味する言葉です。つまり、この言葉を残したパウロ自身も劣等感に悩む一人でした。パウロに親近感がわくとともに、劣等感を抱かない人はいないことを知ることができます。
「私が弱いときにこそ、私は強いからです。」
新約聖書
原語では、「(自分には)弱さがあることを認め、それを管理する」ということを意味する言葉です。「認め・管理する」つまり「自分はなぜ劣等感を持っているのか?」「この劣等感は自分自身にどんな意味をもたらすのか?」をまず「知ろうとして、それを良いものとしてコントロールしていこうとする」ことを意味しています。劣等感を認めることは、過度に劣等感を抱え込まないようにする最初のステップでもあります。
2.劣等感には重要な役割がある(傷を抱えたままで)
先に記した「キリストのゆえに、弱さ…を喜んでいます」という聖書の言葉ですが、「キリストのゆえに」という部分がとても重要です。キリストとは、聖書のテーマでもある「イエス・キリスト」のことです。キリストは、十字架刑の後に復活するのですが、十字架刑で負った手の傷や頭の傷などはそのまま残した姿で復活します。この復活のキリストの姿は、「完全な姿」として記されています。ですが、少し違和感を覚えるのは、「完全であるにも関わらず、傷が残されている状態」ということです。傷がある状態は不完全ではないか?しかし、聖書の価値観は違います。傷や痛みは人間の心の中に常にある状態で、でもそれが人間としての完全な姿であるという側面です。不完全であることがいわゆる完全であり、何も欠けが無い状態で生きることより、傷と共に生きることが人間本来の姿として描かれています。劣等感という傷に思い悩まされるのは、本当に嫌なことです。しかし、不完全さ(劣等感)と共に歩む人間の姿にこそ、人間の本来の姿を表現している。それがキリストの復活の姿に集約されています。歌手の宇多田ヒカルさんがファンとの会話の中で語った「痛みは最初から心の中にある」と語ったエピソードもとても興味深いです。傷や欠けが一つもつない状態を目指すのではなく、傷や欠けを抱えたままで、自分なりの成長を目指していくことの大切さを学ぶことができます。
3.劣等感を分析する
なぜ自分がその劣等感を抱いているのかを分析することが大切です。上記の聖書の言葉に「弱さ、侮辱、苦悩、 迫害、困難」という言葉が記されていますが、ギリシャ語は、後ろに来る単語が前の言葉の原因になっていることが多くあります。よって、この箇所では「弱さ(劣等感)」は、かつて受けた屈辱、苦悩、迫害、困難が原因となっていることを意味します。劣等感を抱くようになるほどの「侮辱、苦悩、迫害、困難」は、自分が本来、目指していたけれども、なんらかの妨害があったために実現できなかった苦しみを意味する言葉でもあります。劣等感を抱くほど苦しみをおぼえるのは、挫折から来ることも多いからです(やりたくないことややらされている中での挫折では、劣等感につながるほどの苦しみを感じることがなく、怒らず傷も受けにくいとアカデミカルな心理学上の研究から解明されています)。よって、劣等感に至るほどの苦しみが具体的にどのようなものであったのかを知ることは、自分のこれまでの足跡を振り返り、本当に自分のやりたかったことを見つけ、人として成長を重ねる原動力にもなります。
例えば、学歴への劣等感について考えてみます。諸事情で大学に行くことができなかった人は大卒者に。自分の第一希望の大学に入れなかった人は第一希望の大学に入った人に。第一希望の大学に入れた人でも、より偏差値の高い大学に入った人に対して、自分が理想としていた目標を成し遂げた人と、成し遂げられなかった自分を比較して、劣等感を抱きます。興味深い点は、例え自分が希望していた学歴を手に入れたとしても、より上位といわれる大学に入った人に対して劣等感を持ってしまうことが起こるということです。日本の一流国公立大学の法学部や医学部などの一流の学歴を手に入れたとしても、今度は日本の大学よりも上位であるとされるハーバード大学など海外の大学に入学できた人に対して劣等感を抱くようになる人が多いという統計データもあります。つまり、これは学歴のケースに限らず、いろいろな劣等感に対して言えることかもしれません。劣等感は、どんなに自分が現状で臨むものを手手にしたとしても、手にした瞬間に際限なく生み出されていきます。
また、別の側面から見えてくるのは、「自分の理想」だと思っていたけれど、実はそれは自分の理想ではなく、「誰かの理想」であり、そこに応えることができなかったという痛みから生み出されたものが劣等感となっているケースもあるということです。他者の期待に応えようとすること自体はとても素敵なことです。問題は、他者の期待に応えようとするがあまりに、そこに応えられない現実の自分に過度な劣等感を抱くようになってしまうことです。よって、自分は何を理想とし、またその理想は誰の理想なのか。その事を立ち止まって考えることはとても大切です。
劣等感と共に成長する
自分が理想としている立場や、物や、環境など、さまざまな事に対して、自分以外の人が輝いてみえ、憧れを抱く。そして、同時に、今の自分はそれらを手にできていないということに強い劣等感を抱く。憧れたり、尊敬したりする思いを持つことは大切なことです。しかし、もう一度、考えるべきことは、それが「本当に自分が目指すべきものなのか」ということを立ち止まって考えてみることです。自分が本当に心から求めることなのか。そこが見失われて、比較の沼に落ちていくと、劣等感を上手にコントロースできなくなっていきます。
聖書に出てくる人物パウロが理想とした自分自身の姿は、ユダヤ人の中で誰よりも知識があり、誰よりも神に関する知識を知り、律法を守り、模範的な人間として存在することでした。実際に、彼は10万人に1人の天才と周りから評価されるような人でした。しかし、「誰よりも」という比較のスパイラルが彼を間違った道に誘います。上にいけばいくほど、「まだ足りない」という思いの中で、自分よりも上の存在、イエス・キリストが自分の目の前に現れたのです。パウロにとって自分よりも輝く存在は邪魔でした。イエスを信じる人たちを殺そうとしたり、イエスを無き者にしようと間違った事に注力しはじめます。ここに、神にはなれないのに、神になろうとするパウロの姿が描かれています。これはパウロだけでなく、私たちにも当てはまる事です。イエスはそんなパウロに語り掛けます。「お前が目指している姿は本当にそういう姿なのか?」と。「あなたは本当はどこを目指しているのか?」を私たちは問われています。
比較の中で育つ劣等感は、解消したと思っても、また次の劣等感がまっています。この劣等感を解決したら、もう劣等感の問題はなくなる…というのではなく、先に書いた学歴への劣等感と同じく、負のスパイラルを繰り返すことになります。劣等感とは解消するものではなく、劣等感というフィルターを通して、自分が本当に求めているものを自分自身に問いただし、出会うために大切なものなのです。劣等感を自分を成長させるものとして活かしていきたいですね。