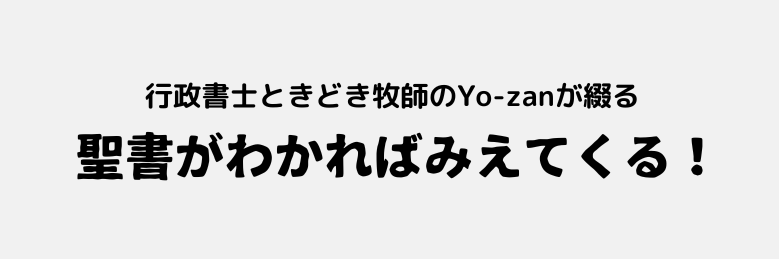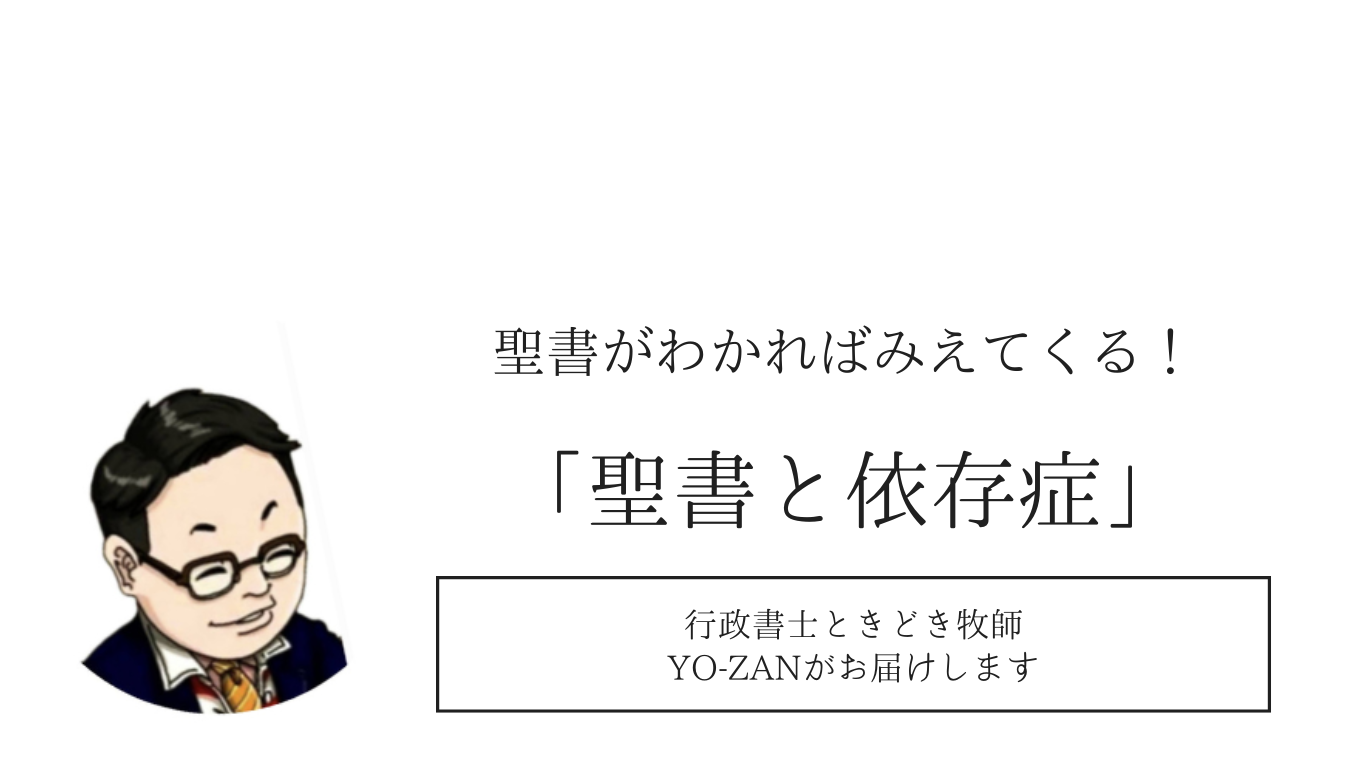アルコール依存症だったかつての自分
「依存していることはわかっている。やめたいとも思っている。でも、どうしてもやめられない。」
必要以上に何かに依存し、そこから抜け出せず苦しい思いをして困った経験はありますか?
私もかつて、どうしてもやめられないことがありました。それはアルコールへの依存です。その要因となったものは何か。私にとっては、中学生の頃に家庭と学校に居場所をなくした経験がとても傷になっていました。当時、居場所をなくした寂しさを私はアルコールで紛らわしました。
しかし、アルコールに依存すればするほど、孤独と苦しみは深まるばかりで健康状態も最悪。社会生活にも深刻な影響を及ぼしました。中学生の頃から大学時代までアルコールへの依存は続きました。スキンヘッドにうつろな目をして、常にお酒の匂いを漂わせていたのがかつての自分でした。
「お酒はやめたいけど、やめるくらいならば死んだほうがましだ。でも、生きていたいから酒を飲む。」と、矛盾だらけ、葛藤だらけの状態に身も心もたたずみ、「ま、いっか。お酒飲もう。」と開き直らないと生きていけない、そんな苦しい日々を過ごしました。
厚生労働省のサイトによると、依存症の一つである薬物乱用のための医療コストが2000億を超え、依存に苦しむ人が年々増加傾向にあると記されていました。また、薬物以外にも依存症と診断される人の数が増加している統計もあります。
近年の「依存」に関する研究において、依存症は、条件がそろえば誰しもが陥る可能性があり、特別な人だけが陥るものではないということもわかってきています。
このページを読んでくださっている皆さんも、やめたいと思いながらもやめることができない、苦しみを伴う依存の習慣はありませんか?もしくは過去にありましたか?
今回は、やめたいと思っていてもやめることができない、そんなアルコールへの過度な依存の症状から、私自身が脱却する助けとなった聖書からの知恵について書いていこうと思います。
依存症のいろいろ
(1)依存症とは何か
まず最初に「依存症とは何か」を見てきます。
依存症とは、「ある特定の物質や行動に対して、やめたくてもやめられない状態に陥ること」です。また、それが常態化すると、心身にも悪影響を及ぼします。有害物質を摂取することに依存している状態であれば、それが長期化すればするほど、身体に直接的ダメージを与えます。また、依存している行動や物質が第一に優先されるため、睡眠や食事など、日常の生活習慣にも悪影響を及ぼします。
また、依存する物質に対しての行動が自分の中での最優先事項となるため、時には他者を依存対象物を手にするための道具として利用してしまったり、相手が傷ついても構わないという自己中心的な心理状態に陥り、自分の関わる人に実被害をもたらしてしまうこともあります。周囲の人から警戒され、孤立し、社会から爪はじきされることも実際あります。このように、依存症は自分に限らず、周囲の人々の心身にも、さらには社会的にも大きな被害を及ぼすことも。
(2)依存症の種類と依存症克服のためのアプローチ
依存症は大きく分けて、物質への依存とプロセスへの依存の2種類があります。
物質への依存とは、アルコール依存症、麻薬依存症、ニコチン依存症、処方薬依存症、カフェイン依存症、糖質依存症など、特定の快楽や刺激をもたらす物質への依存状態のことを指します。
プロセスへの依存とは、ギャンブル依存症、恋愛依存、パチンコ依存症、買い物依存症、ネット依存症、スマホ(携帯電話)依存症など、特定の行動やプロセスに対する依存状態のことを指します。
以前は、物質的依存は依存性物質を体内に取り入れた結果として、依存状態になるので依存性物質を完全に抜くことで依存状況を脱することができるとされていました。
また、プロセスへの依存は、依存性物質を体内に取り入れるわけではないので、自分の意志の力、つまり自力で立ち直れるものと以前は考えられていました。
しかし近年の心理学や医学の研究によると、物質への依存は依存性物質を体から抜ききったとしても、再び同じ物質への依存がおこることがわかっています。また、プロセスへの依存も、意志の力だけで失敗する事例が多く、さらには、一時的に依存症状態を抜け出せたとしても、長期間の継続は難しいことが判明してきています。体内に何らかの依存性物質を取り込むわけではないのに、依存性物質を取り込んだのと同じ状況が起こっていることもわかり、意志の力だけで乗り越えるのは難しいことも判明しています。
物質への依存も、プロセスへの依存も、より複雑な要素が絡み合っていると考えられるようになってきています。その結果、依存症の原因ははっきりと特定されずに、様々な学説も存在します。
私自身も、アルコール依存症まっただ中の頃、医学的アプローチやカウンセリング的アプローチを用いたりもしましたが、一時的に脱却することがあっても、しばらくすると元通りに戻っていました。そんな事を繰り返す自分の意志の弱さに落胆し、死を意識するまでになりますが、そんな気持ちを打ち消すために、またアルコールに手を出すという悪循環の中に生きていました。
アルコール依存からの脱却を目指す中、依存症克服には大きく分けて二つのアプローチがあることを知りました。
➀依存症を「脳の病気」と捉える考え方
依存症は病気であり、自力で治癒することは不可能と考え、医学的なアプローチによってのみ治癒に至るという考え方です。しかし、依存症を抱える多くの日本人は、依存症であるということを「恥」と考える傾向が強く、医学的治療を受けようとしない人が多いのが現状です。
そこで医学的なアプローチをとる場合は、まず自分が依存症であり、自力では抜け出すことができない病気であることを受け入れたうえで、医学的アプローチに至らせるためのカウンセリングが実施されます。
私自身も、カウンセリングを受け、アルコール依存を一時的に脱却することはできました。しかし、医学的な治療機関から離れた後、比較的早い段階で、再び依存状態に戻ってしまったという経緯があります。医学的アプローチは間違いではないのですが、医学的アプローチのみでは、一時的脱却の後、再び依存状態に戻ることを繰り返していました。
そんな状態でしたから、当時は自分の意志の弱さを責めました。しかし、後にわかることは、70%近くの人が、医学的アプローチで克服したと思っても、再び依存状態に戻ってしまうケースもあり、私だけではありませんでした。
繰り返しますが、医学的アプローチは一時的ではあったにせよ、依存状態から脱却することに成功することは多いので、間違っているアプローチではありません。しかし、私の場合は何かが足りなかったのです。
②依存症を「自分の選択」と捉える考え方
依存症は、自分で自分に快楽や刺激を与え続ける物質の接種や行動を選び続けた結果だという考え方です。この考え方に基づくアプローチでは、医学的なアプローチを用いることなく、依存症を最初に選び取るに至った原因を探り、その原因となった問題を解決することで、依存状態から自分の意志で脱却することができるという考え方です。
しかし、このアプローチの方法でも、私自身のアルコール依存症が回復するのかといえばそうではありませんでした。短期間で元に戻ってしまいます。例え、依存症に陥った原因が解決されたとしても、一度何かに深く依存した経験をもつと、その時の刺激や快感を脳が完全に記憶し、再びその時の刺激や快楽を求めてしまう性質が私の中にあるからです。軽度の依存症であれば、このアプローチにより一時的にでも依存症から脱却できることはありますが、なぜか抜け殻のようになり、次第に漠然とした不安をいつも抱えている状態になり、結局また何かに深く依存する症状に戻ってしまうのです。
依存症とは違った、他の精神的疾患などでも、回復後に抜け殻のような状態になることは起こるそうです。異常心理学者の第一人者であり、元アメリカ心理学学会の会長のセリグマン博士も、鬱をはじめとする多くの精神疾患から回復したはずの人が、なぜか抜け殻のような状態になり、生気が失われてような状態になることをレポートしています。
もちろん、依存症に陥った原因を追求することは重要なプロセスの一部です。しかし、依存症脱却という目標に到達したとしても、しばらくすると、またすぐに依存状態に戻るのであれば、これらのアプローチも医学的アプローチと同じで、間違ったプロセスではないけれど、何かが足りないのです。
このように、私自身、依存症を克服しようと様々な専門家の見解、また専門書などで調べたのですが、結局、有効な解決方法を見つけることができず、当時は絶望を極めました。
しかし、そんな中、かすかな光となった存在がありました。たまたまNHKで放映されていた「こころの時代」のキリスト教特集でした。そこで朗読された聖書の言葉が、新約聖書ローマ人への手紙6章16節でした。「あなたがたは知らないのですが。あなたがたが自分自身を奴隷として献げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となり義に至ります」
この言葉を切り口に、聖書と、聖書の視点からの心理学、医学的観点、この3つから、依存症を克服する術が、私なりにですが見えてきました。
聖書の視点から~依存症を乗り越えるための方法
Ⅰ、依存症は聖書ではどう語られているか?
➀「罪の奴隷」から考える依存症
先ほど引用した聖書の言葉の中に「罪の奴隷」という言葉があります。聖書において「罪」というのは、「高慢」を原義とする「ハマルティア」というギリシャ語で表されている言葉です。周囲に迷惑をかけたり、傷つけたり、破壊したとしても、自分だけ快楽を得ようとする「自己中心的な行動」を意味する言葉です。
「奴隷」は「主人に負債を負ったしもべ」を原義とする「ドゥーロス」というギリシャ語で表されている言葉です。主人に対して負債を負い、自分ではその状況から抜け出せない状態、また習慣となった癖などを意味する言葉です。
つまり、「罪の奴隷」とは、「快楽を得るための行動から抜け出せず、それが習慣化された状態」を意味しています。これは、まさに「依存症」とほぼ同じような意味を持っています。
さらに、「罪の奴隷」になるということは、最終的に「死」に至ることであると記されています。聖書でいう「死」とは二重の意味があり、第一の意味は肉体的な死です。そして、第二の意味は道徳的な死といわれています。この聖書の箇所が語る死は第二の死、つまり道徳的な死を意味します。道徳的死とは永遠に周囲の者と断絶されること。つまり[永遠の孤独]を意味する言葉です。周囲の迷惑を顧みずに刺激や快楽を求め続ける状態(=罪の奴隷)になると、最終的には自分の心身の健康を害し、死を早めるだけでなく、他の何者とも関係を持つことができなくなる永遠の孤独という苦しみがまっていることを意味します。
心身の健康を低下させ、肉体的な死の危険をもたらすだけでなく、社会からも孤立していく状態におちいる「罪の奴隷」と「依存症」は同義ともいえる言葉です。
では、「罪の奴隷」が依存症であるならば、「罪の奴隷」と対句になっている「従順の奴隷」という言葉には、どのような意味があるのかを見ていきます。
②「罪の奴隷」と対極にある「従順の奴隷」について
「従順」とは、「秩序」を原義とする「イュパコイ」というギリシャ語が使用されています。「秩序」というと堅苦しく聞こえるかもしれませんが、聖書でいう「秩序」とは、自分だけでなく周囲のことも大切に思いやりながら行動することです。存在するすべてのものを大切に思う気持ちこそが大切なことだということを意味する言葉です。
よって、「従順の奴隷」とは、自分や他者を大切にすることに喜びを感じ、その状況を大切にする姿を示しています。
アメリカ心理学会の元会長であるセリグマン博士は、人間の幸福(ウェルビーイング)を感じる度合いを高めるための大切な要素の研究を行いました。その研究によると、医学と心理学の統計データから、「人間関係」と「熱中するもの」の数値が高ければ高いほど、脳波や体内物質の総量の数値が、前向きな気持ちとなっていると想定される数値を示したそうです。近年、モチベーションアップにつながる体内物質として、ドーパミンという言葉を聴いたことがある方も多いと思いますが、何かを大切に思い、行動しようとすればするほど、ドーパミンが放出され、モチベーションが高まり、前向きな気持ちになっていくという研究結果でした。
このように、聖書からの言及とともに、客観的なデータからも何を大切にすべきかが明らかになっています。
そして「従順の奴隷」となると、「義」に至るということも記されています。聖書において「義」はギリシャ語でディカイオシュネーという言葉が使われていますが、原義は「関係における正しさ・美しさ」と原義される言葉です。
Ⅱ、依存症を乗り越えるためのヒント
「罪の奴隷」と「従順の奴隷」について、その意味を深掘りしていくと、人間に備わっている大切な性質が見えてきます。それは、人間が何かに依存したり、頼ったりすることについて、[否定はしていない]ということです。それどころか、「義」にいたるための大切な性質であるとしています。
聖書は、人が何かに依存したり、頼ろうとすることは、とても大切な[性質]であると一貫して教えています。そして、ここに依存症を乗り越えるための一つの結論が見えてきます。それは、依存症克服のゴールは「依存症をなくす」ことではなく、「正しいものに依存する」状態になるということです。つまり、「依存する対象を正しいものへと変える」ことが大切だということです。
自分はこのことを知った時、驚きとともに心からの平安を得ることができました。今では、完全にアルコール依存症を乗り越えました。日常の生活で飲酒をすることはまったくありません。時々、祝宴の場などでたしなむ程度です。そこからフラッシュバックするということもありません。
どのようなステップで私自身がアルコール依存症を乗り越えたのか振り返ってみます。
私が経験したアルコール依存からの回復のステップ
➀「依存状態そのものは悪いことではない」ことを知る
前述のように、人間が何かに依存すること自体は悪いことではありません。まずはそのことを知識として知ることがとても大切です。しかし、何かに依存している状態から生きづらさを感じるなら、依存する対象を正しいものに替える作業が必要になってきます。
新約聖書のヨハネの福音書8章32節には、「真理はあなたがたを自由にする」という言葉があります。依存という性質に対する正しい理解を深めれば深めるほど、自分や他者を大切にすることへの「依存」にシフトを変え、喜び(自由)を手にすることができる経過をたどります。そんな喜びの中に自分の心も体も満たしていくことで、悪癖から解放される一歩を踏み出していきます。
②自分一人の力では依存症を克服できないことを知る
「私のからだには異なる律法があっ て、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を、からだ にある罪の律法うちうちにとりこにしていることが分かるのです。私は本当にみじめな人間 です。 だれがこの死のからだから、 私を救い出してくれるのでしょ う か。」(新約聖書・ローマ人への手紙7章23・24節)
この言葉はパウロという人物が、「従順の奴隷」となる喜びを知りつつも、かつての悪癖から抜けせず、「従順の奴隷」から「罪の奴隷」に何度も逆行してしまう葛藤を述べた言葉です。
このパウロという人物は、世界史の教科書にも名前が出てくるほど、キリスト教会を中東とヨーロッパ全土に広めたといわれる人物です。世界史にも出てくるほどの人物でありながらも、なんらかの依存症に苦しんでいた葛藤を告白しています。
本来ならば隠しておきたい自分の弱さを、なぜパウロは公に告白したのでしょうか。なぜ、自分の弱さをさらけ出すことができたのでしょうか。このパウロの告白を読み深めてわかるのは、自分の意志の力だけでは抜け出せないのが依存症であり、告白を通して自分以外の人に助けてもらうことが大切であると私たちは学ぶことができます。
しかし、「罪の奴隷」を自分の身体から切り離す過程では、自分の心に痛みをもたらすことがあります。そして、この痛みを越えた先に、「従順の奴隷」となる喜びもおとずれます。パウロもその事実について聖書に記しています。
「苦難さえも喜んでいます。 それは、苦難が忍耐 を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。」(新約聖書・ローマ人への手紙5章3-4節)
この「痛み」が訪れる時、かつての「罪の奴隷」の時に得た刺激、快感を得る物質や行動の記憶が脳に残っているので、痛みから逃れたいがあまりに、「罪の奴隷」の状態へと後退してしまうこともあります。
聖書では、「罪の奴隷」を自分の身体から切り離す時に訪れる痛みのことを「苦難」と表現していますが、「苦難」とは自分では忍耐できないほどの苦しみを表現する言葉です。つまり、自力では「罪の奴隷」を切り離す痛みに耐えることはできないのが実状です。だからこそパウロはその苦痛を、他者からのサポートをしっかり受けることで乗り越えました。
私自身の体験として、医学的サポートやカウンセリング的サポートは、一時的に依存症を抑え込むことにはとても有効なものでした。しかし、症状を抑え込むだけでは、結局は抜け殻のような状態になるだけで、やはりいつも漠然とした不安を常にもっていることに変りはなくて、結局は依存症へと逆戻りしていました。
しかし、聖書からの学びを経た後は、医学的サポートやカウンセリングを併用しつつ、新たな生き方である「従順の奴隷」として「自分や他者を大切にする喜び」について、「罪の奴隷」としての刺激や快楽以上の喜びがあることを自分自身に体験させ続けました。その時も、周りの人に助けを求めることを恥とせず(初めはとても躊躇しますが)、また依存そのものは何か自分の中に理由があっておきていて、依存という性質を悪とせず、大切なもの、意味あるものとして、より丁寧に扱いことを心がけました。
私のケースは、自分自身が中学時代に居場所を無くした経験から、同じような思いをしている子どもたち、助けを必要とする子どもたちの力になることで、マイナスの依存(アルコール依存)から、プラスの依存(自分や他者のために動く行動)へ、自分自身の依存に対する習慣を切り替えていきました。マイナスの依存の行き着く先は孤立の状況を生み出したりしますが、プラスの依存は、共存、支え合うことを生み出し、必要なときに助けを求める関係も築くことができ、またそこに生きずらさは伴いません(他者のために!に隠れた自分の為に!が強調されすぎる「共依存」とはまた違います)。
まとめ
・何かに依存する性質は悪ではない。人間に備わった大切な性質の一部。しかし、過度の依存で自分自身が生きづらさを感じたり、周りの人に迷惑がかかるような状態はやはり問題として扱うべき。
・一度依存症になったら自力での解決は難しい。自分一人では解決できない弱さを認め、医学やカウンセリングを通し自分の苦しみを語る場をもつ。
(自己開示も心理学では依存症からの回復に有効であると研究で明らかになっている)
(自己開示は誰でもいいというわけではなく、もちろん自分が信頼できる人に)
・依存する対象を「自分や他者を大切にすること」に変換することを目指す。
今回は、私自身が経験したアルコール依存について主に書きました。解決策は個々人で違いますが、私自身のアルコール依存症から抜け出したプロセスを聖書からの知恵と照らし合わせて記録してみました。
お読みいただきありがとうございました。